【なぜ脳は因果関係を決めつけたがるのか?】

💡 「この出来事の原因はこれだ!」
と決めつけたこと、ありませんか?
例えば…
- 家を出て暗い雲を見たら「あ、雨が降りそうだ」と思う。
- ある歌を聴いたら、ある特定の思い出がよみがえる。
ところが、実際にはすべての出来事が因果関係で結びついているわけではありません。
では、脳は 何をもとに因果関係を決めているのでしょうか?
私たちの脳は「因果関係」を一体どうやって決めているのか。
🧠 脳は“予測マシン”

脳の機能を理解する上で、必要なのは「脳は毎秒、未来を予測し答えを検証している」という事実です。
これは、いわゆる「Predictive Processing Theory(予測処理理論)」と呼ばれるもので、カール・フリストン(Friston, 2010)が提唱しました。
たとえば…
🐻 森で野生の大熊に遭遇したら「逃げるべき!」と脳は判断しますよね?
👉 これは 過去の経験や知識を元とした情報を脳が因果関係をある種の「プログラミング」と照らし合わせて予測した結果です。
💡 でも、このシステムには欠点があります。
気をつけなければならないのは、この予測システムは実際には間違いを含んでいることが多いということです。
人は、実はあるはずのない因果関係をでっちあげることがよくあります。
🔬 実験:脳は“因果関係”をどこまで信じるのか?

👨🔬 ジョージ・バイコブ博士 と アンドリュー・ホール博士は、私たちの脳がいかに無意識に因果関係を認識してしまうかを研究しました(Baillargeon et al., 1985)。
🔍 実験内容
- 被験者にランダムに点滅する光のパターンを見せる
- その光の点滅に意味を見出すかどうかを観察
📊 結果:
🔹 ほとんどの被験者が 「特定の光のパターンが次の点滅を引き起こす」という誤った因果関係を信じ込む傾向があることがわかりました。
これは、私たちの脳が「パターンを見つけること」に非常に長けていることを示しています。
実際、進化的な観点から見れば、因果関係を素早く推測できることは生存に有利でした。「この音がしたら、捕食者が近くにいるかもしれない」と考えることで、危険を回避することができたのです。
⚠️ しかし現代では、この脳の特性が時に誤った信念やバイアスを生み出す原因にもなります。
🎭 因果関係の罠:思い込みが現実を作る?

例えば…
👕 試験に合格した日に赤いシャツを着ていた
👉その経験が「赤いシャツを着ると成功する」という思い込みにつながることがあります。
🏆 スポーツ選手がゲン担ぎのルーティンを持つのも同じ心理です。
⚠️注意:アンカリングとは違います。
また、失敗を繰り返すことで「自分はダメな人間だ」と決めつけてしまうこともあります。
👉しかし、失敗の本当の原因は、単に学習方法が合っていなかっただけかもしれません。
でも、これらは 本当の因果関係ではなく、ただの偶然かもしれません。
💪 因果関係を見極める力を鍛えるには?
成長のために因果関係を書き換える方法

良いニュースがあります。
それは、脳は常に適応し続けているため、「因果関係の解釈を変えることができる」ということです。
🔍 脳の思い込みを防ぐために、次の習慣を取り入れましょう!
思い込みを疑う
「自分にはいつもこういうことが起こる」「私は絶対に○○できない」などと考えたとき、一度立ち止まってみてください。
「これは本当に事実なのか? それとも、脳が作り出したパターンなのか?」と問いかけてみましょう
又、「これは本当に因果関係があるのか?」と自問するクセをつけて下さい。
データを集める=別の原因を探す
物事がうまくいかなかったとき、「自分がダメだから」と短絡的に結論を出さないこと。
「このプロジェクトが失敗したのは、自分の能力が低いから」ではなく、「戦略を見直すべきだったのかも?」と考えてみると、新たな可能性が見えてくるかもしれません。
そして、1回の出来事だけで判断せず、 複数の事例を確認するのも良いかもしれません。
新しい関連付けを作る=別の視点を取り入れる
脳は「失敗=恐怖」を結びつけることができるのと同じように、「努力=成長」と結びつけることもできます。
ミスを「障害」ではなく「学びの機会」として再解釈してみましょう。
自分の解釈が本当に正しいのか、他の視点で考えてみることを試してみて下さい。
その上で、「他の人が見たらどう感じるか?」と考えてみるいいかもしれません。
脳に「可能性」を見せる=新しいパターンを作る
古い思い込みを打ち破るたびに、脳は新しい神経回路を作ります。
挑戦することで、脳の「因果関係マップ」を書き換えることができるのです。
ネガティブな思い込みをポジティブなものに書き換える習慣をつけることを試してみて下さい。
例えば…
「自分はプレッシャーに弱い」と思い込んでいるアスリートが、試合前に視覚化トレーニングを取り入れるとします。
「自分は本番に弱い」という思考から、「私はプレッシャーを乗り越えられる」という思考へと少しずつ書き換えられていきます。
これを続けることで、実際のパフォーマンスも向上していくのです。
📌 まとめ

私たちの脳は常に因果関係を見つけようとします。
しかし、その推測が必ずしも正しいとは限りません。
だからこそ…
✅ 自分の思い込みを疑うこと
✅ 自分のパターンを見直すこと
✅ 事実を冷静に見ること (それ事実、それとも解釈?)
✅ 新しい可能性を探る
これを意識することで、 より正しい判断ができるようになります!
自分に問いかかけてみて下さい、
見直してみることで、新しい未来が開けるかもしれません。
📚 参考文献
- Baillargeon, R., Spelke, E. S., & Wasserman, S. (1985). Object permanence in five-month-old infants. Cognition, 20(3), 191-208.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127-138.
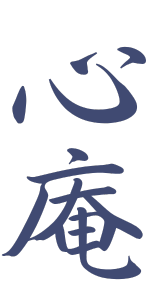



コメント